
アニメや漫画原作の実写化映画のイメージを聞くと。
- つまんない
- 安っぽい
- パッとしない
- 原作と違う
というイメージを持つ方は多いと思います。
しかし、ハリウッド作品に目を向けると
マーベル作品の実写化映画(「アイアンマン」「スパイダーマン」)や、ディズニー映画の実写化映画「アラジン」「美女と野獣」「マレフィセント」「シンデレラ」など傑作はたくさんあります。

というとそんなわけはなくて、誰もが知っているように、日本の漫画やアニメは世界的に大ヒットしている作品がたくさんあります。
もちろん人気もあります。
つまり、原作(ストーリー)は間違いなく面白いのです。
にもかかわらず、なぜ実写化映画で邦画だけがこんなにも”つまんない”作品が多いのか?
この記事で解説していこうと思います。
そして記事の最後では、これを読むと”映画の観方が変わる”一冊の本を紹介します。お楽しみに。
この記事で分かること
- 日本のマンガ原作の実写化映画がつまらない理由
- 小説、マンガ、アニメ、映画、舞台の表現方法の違い
- 日本の映像作品や舞台が面白くなるヒント
アニメ原作の実写化邦画がつまんない四つの理由

なぜ漫画の実写化作品で邦画だけにつまんない作品が多いのか?その理由は、全部で四つ
- 日本の漫画がそもそも実写化に向いていない
- アニメ作品の出来が良すぎる
- 制作費が少なすぎる
- スポンサーが出資しやすい
それぞれ解説していきます。
1、日本の漫画の設定がそもそも実写化に向いていない
そもそも日本の漫画が実写化に向いていない作品が多いんです。
どういうことか?
原作の漫画やアニメは面白いのに実写化に失敗した作品に共通するのは
ポイント
- 主人公などのキャラクターの年齢設定が若い
- 舞台設定が現実離れしすぎている
- 週刊連載で長期の作品
- 絵
 が特徴的
が特徴的
という傾向が強いです。
主人公などのキャラクターの年齢設定が若い
日本のマンガ、特に少年マンガは年齢設定が小学生から高校生の作品がやたら多くないですか?
『鋼の錬金術師』『進撃の巨人』『斉木楠雄のΨ難』『暗殺教室』例えば最近では『永遠のネバーランド』など
⇩きになる原作のマンガが、【タダ本】だと無料(タダ)でもらえる⇩
10代、しかも小学生の年齢から高校生の年齢が多い傾向があります。
それを実際に実写化する場合、キャスティングされる役者さんの年齢は二十歳を超えている方がほとんどではないでしょうか?
そんな大の大人たちが高校生を演じて違和感が生じるのは当然だし、
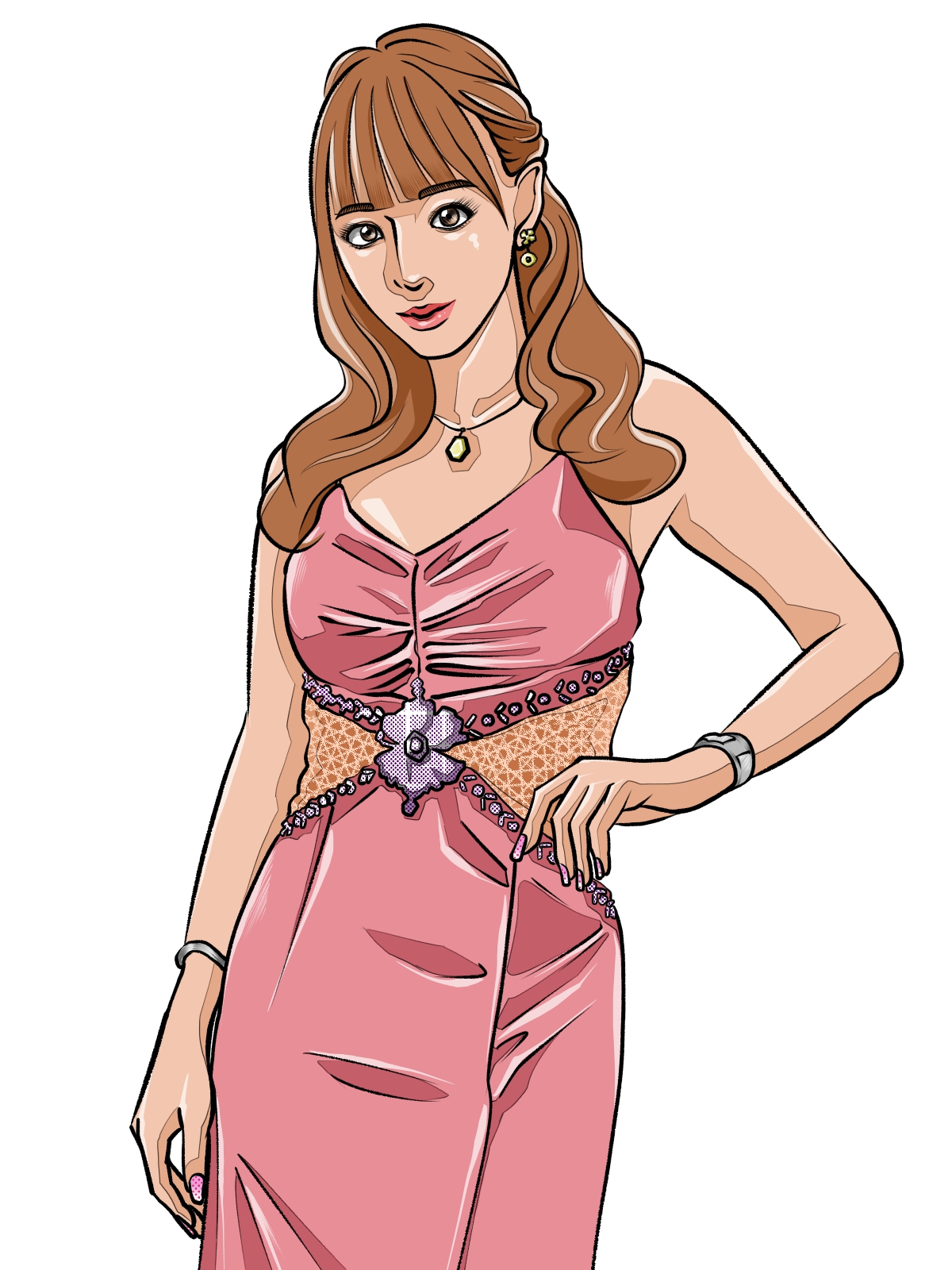
といわれてもしかたがありません。

と思うかもしれませんが、実はそうはいきません。
なぜか?
理由は簡単です。

売れていない役者さんを使っても、話題性はありません。
当然話題性が薄くなると、興行収入も減ります。
興行収入が減るなんて、そんなものお金を出資している”スポンサー”や出資もしている”芸能事務所”の意向に沿うわけがありません。
では、年齢設定の低い作品を、お客さんの呼べるキャスティングでどうやって実写化すればいいのか?
答えは”原作の年齢設定を変更する”のです。
しかし、年齢設定を設定を変えてしまう問題が起きます
それは、その年齢っだからこそ成立するシーンが全く機能しなくなります。
もちろん、原作の良さも消えるわけですね。
『約束のネバーランド』なんて、その典型ではないでしょうか。
メモ
原作では主人公たちの年齢設定は最年長キャラでも12歳の少年少女たちです。
その年齢の子供たちが”その年齢であるが故のある理由で”命を奪われる”から、その施設から逃れるため、死なないために知恵を絞って切り抜けていくサバイバル作品です。
にもかかわらず、その年齢を16歳まで引き上げられてしまいました。
そんなの元も子もありません。
根底からひっくり返すことになります。
一方ハリウッド作品での登場人物は、大人な年齢のキャラが多いのではないでしょうか?
舞台設定が現実離れしすぎている
原作の漫画の舞台設定が特徴的な作品が多い傾向があるからです。
「進撃の巨人」なんてその最もとなる作品ではないでしょうか?
そもそも巨人が出てくる時点で相当特殊な作品ですよね。
また巨人や、立体機動装置を実写化するのにどれ程の手間と時間がかかることか。
もう一つの例として「ドラゴンボール」もそうです。
この作品もかなり特徴的ですよね。
サイヤ人や人造人間、魔人ブウなんてどう実写化すれば、リアルさを表現できるのでしょうか?
マンガの人気作品は週刊連載で長期の作品が多い
日本のマンガは、週刊誌や月刊誌で連載されている作品がほとんどです。
そして人気作品ともなれば連載期間は何年も続くので、当然長期連載となります。

あなたがその原作の漫画を最初から最後まで読むとしたら、どれだけの時間がかかるでしょうか?
もし、そんな内容長くて濃い内容の話を2時間でまとめるとしたら、話を間引くしか方法がありません。
つまり映画用に、新たに台本を書き直すわけです。
これは必然です。
そもそも漫画のボリュームを、映画二時間にまとめようとするのが無茶な話なのです。
例えば映画の「キン●ダム」なんて、単行本の1~5巻の46話までを、二時間ほどに収めるって無理な話ですよね。
それりゃー説得力ない作品になるわけです。
映画見てみましたが、圧倒的に情報が不足しているのですからね。
当然原作を読んだことがある人が映画を見たら、その内容の薄さに怒りがこみあげてくるでしょう。
これだったら、総集編のがまだマシです。
まぁ総集編にお金は払いたくないけどね。
小説の原作実写化映画も内容がスカスカ
同じように、邦画には小説原作の映画作品が多いです。
そもそも小説の表現方法と、映画の表現方法が違うです。
小説の内容を、短時間でまとめるという行為自体ナンセンスなんですよね!
当然作品は120%つまらないものになりますよね。
絵が特徴的
この【絵が特徴的】という理由が、マンガ原作の実写化映画がつまらない理由として、とても的を得ていると個人的には思っています。
日本の漫画って世界と比べてみても、絵がとても特徴的だと思うんです。
メモ
これは、長年日本の漫画家さんが、週刊誌で毎週原稿を書いていく中で、人の感情やアクションを表現するために、絵というか線だけで、コマ割りなどを用いて演出や表現を追求してきた結果だと思います。

ジョジョの奇妙な冒険や北斗の拳なんかとても、絵が特徴的ではないでしょうか?
アニメ化の場合はその特徴的な絵をそのまま使えるので、中で生きているキャラクターの感情や表現が伝わるのです。
だがもしそれを生身の人が演じてしまったら、絵であるからこその”良さ”を全くの”0”にしてしまいます。
逆にハリウッド作品のマーベル作品なんかだと原作の絵は、現実の人に近い描写ではないでしょうか?
2、アニメ作品の出来が良すぎる
原作のマンガが面白いのはもちろんですが、アニメ作品がとてもよくできている作品が多いのも、実写化のハードルを上げている一つの要因です。
最近流行った『鬼滅の刃』や、最近とても人気のある『呪術廻戦』なんて、アニメーション技術や演出がとても素晴らしいですよね。
あまりにもアニメの出来がいいので、アニメから原作の漫画を買うなんて人は最近とても多いはずです。
もちろんそんな漫画をわざわざ実写化するのですから、原作を”ある部分”では超えなければ、そもそも実写化作品を作る理由がありません。
しかし、先に制作されているアニメーションの出来が良すぎるから、実際に実写映画化したところでアニメを超えるなんてことは、万が一、いや億が一もあり得ないのです。
3、制作費が少なすぎる
日本の漫画やアニメを実写化するにあたって、その制作に費やされるお金がハリウッド作品と比べると圧倒的に少ないのが原因のひとつです。
原作はとても面白いく、世界観が独特で表現が難しい作品が日本では多いし、そんな特徴的な漫画を実写化するんですから、それ相応の技術と時間が当然必要になりますよね。
つまり、お金がメチャクチャかかるのです。
ハリウッド作品では、漫画が日本の作品より独特ではないし、かかっている製作費の日本と比べると桁が違います。
当然その金額の差は、作品の出来にも大いに反映されるのは当然といえば当然です。
4、スポンサーが出資しやすい
では、なぜ実写化映画が失敗する可能性が高いのに、アニメ原作の映像作品が後を絶たないのでしょうか?
理由は簡単です。
儲かるから。
まぁ大事なことなんですけどねー。
漫画・アニメ大国日本で、その関連実写化作品の特徴は
注意ポイント
- 一定の需要が予測できる
- 何より原作があるからスポンサーさんにプレゼンしやすい

そしてスポンサーには、芸能事務所やテレビ局が出資していることが多いです。
大手芸能事務所が出資するので、必然とその事務所が推ているの演技力のないタレントが、役者として出演することが多くなります。
人気があるタレントやアイドルなら、そのファンが見に来てくれるので、その映画のある程度の売り上げが期待できるし、ある程度の需要が予測できます。
だから、結果的に出資もしやすいわけです。
邦画の作品に「アニメ」や「漫画」題材の実写化作品が多いのも、そういった芸能界の体制のせいでもあります。
日本の映像作品(テレビドラマや映画)にやたらアイドルが起用されるのも、日本の芸能界の体制のせいです。
アニメ原作で演技力が高いわけでもない事務所推しのタレントが出ている作品が多いから、つまらないのです。
まぁ演出する側が圧倒的に力不足なんですけどね。
きちんと、監督さんが役者さんを演出してあげればいいのです。
※もちろん面白い作品もあります。『るろうに剣心』の実写版は、今年4作目と5作目が上映予定。
面白い作品となった要因を自分なりに考察しています。
-

-
『るろうに剣心』実写化映画の評価がなぜ高いのか?その秘密を解説
今年2021年4月23日に第四作『るろうに剣心 最終章 The Final』と6月4日に第五作『るろうに剣心 最終章The Biginning』の上映が予定されている、実写版『るろうに剣心』。 &nb ...
続きを見る
各々の表現媒体の特徴

表現媒体にはそれぞれ別々の特徴があって、それぞれに適した物語が展開され、完結しています。
小説の良さ
文字による
- 心理描写
- 行動描写
- 情景描写
- キャラクターの台詞
で成り立つ。
読む人の文字からの想像力に委ねる部分がほとんどを占める。
マンガの良さ
小説と違って
- 台詞以外の心理学描写
- 情景描写
を絵で表現する。
小説より、絵(視覚)での表現があるため、読者の想像力にゆだねる部分が”文字だけの小説”より少ない。
絵がある分、小説より簡単に読める。
コマとコマの間は読者の想像力で補う。
アニメの良さ
絵が静止画ではなく動画で表現して、編集で演出効果をだせる。
声を加えることでのキャラクターを具体的に表現
動画による
- 動きの壮大さ
- スピード感
音楽での緊迫感などの効果も加える
これらの演出により、マンガよりも更にその世界に入り込みやすい。
視聴者の想像力は心情の部分に占められる。
舞台の良さ
目の前に生身の人間がリアルタイムで表現するので、観劇者は、
- 人の声
- 息づかい
- 生身の空気感
- 緊張感
を直に体験できる。
最もリアルに近い表現方法。
ただ、劇場の大きさにより、役者さんの表情方法が変わる。
またライブで提供されるので、同じ演技は二度と見ることはできない。
映像の良さ
人間による表現方法。
ただ、舞台と違って、
- マイクにより声も拾える
- カメラで拡大することもできる
- 役者さんの声のボリュームも小さくても成り立つ
また舞台と違って声をはったりするひつようがないので、役者さんはより日常に近い表情方法で演技ができる。
編集による演出効果を表現できる。(アニメと一緒。)
アニメと違うのは
- 生身の複雑さ
- 癖
- 表情表現の豊かさ
は生身が演じているからこそ。
実写化映画化する際に生じる弊害

小説を映画化するには

なぜか?
映像は生身の人が演じるので、人や景色からの情報が増えます。
その分、セリフを減らす必要があります。
そのためには、原作を分解して再構築、そこに演出を加えなければなりません。
もちろん原作が面白いから映画化されるのですから、原作の完成度は物凄く高いはず。
その作品を改めて作り直すハードルの高さは、とんでもないことになります。
原作のファンを納得させるには、同じくらいではダメだと思います。
原作より完成度の高いものを求められる。
じゃないと作る意味はないはずです。
漫画やアニメを映像化するには
漫画原作の映画も同じく、あのボリュームを映画のわくに納めようとしたら、ダイジェストになるか、無理矢理まとめるかしかありません。
だからもし漫画を映画にいするなら、設定だけ借りて、映画オリジナルストーリーにしたほうが断然面白いのです。
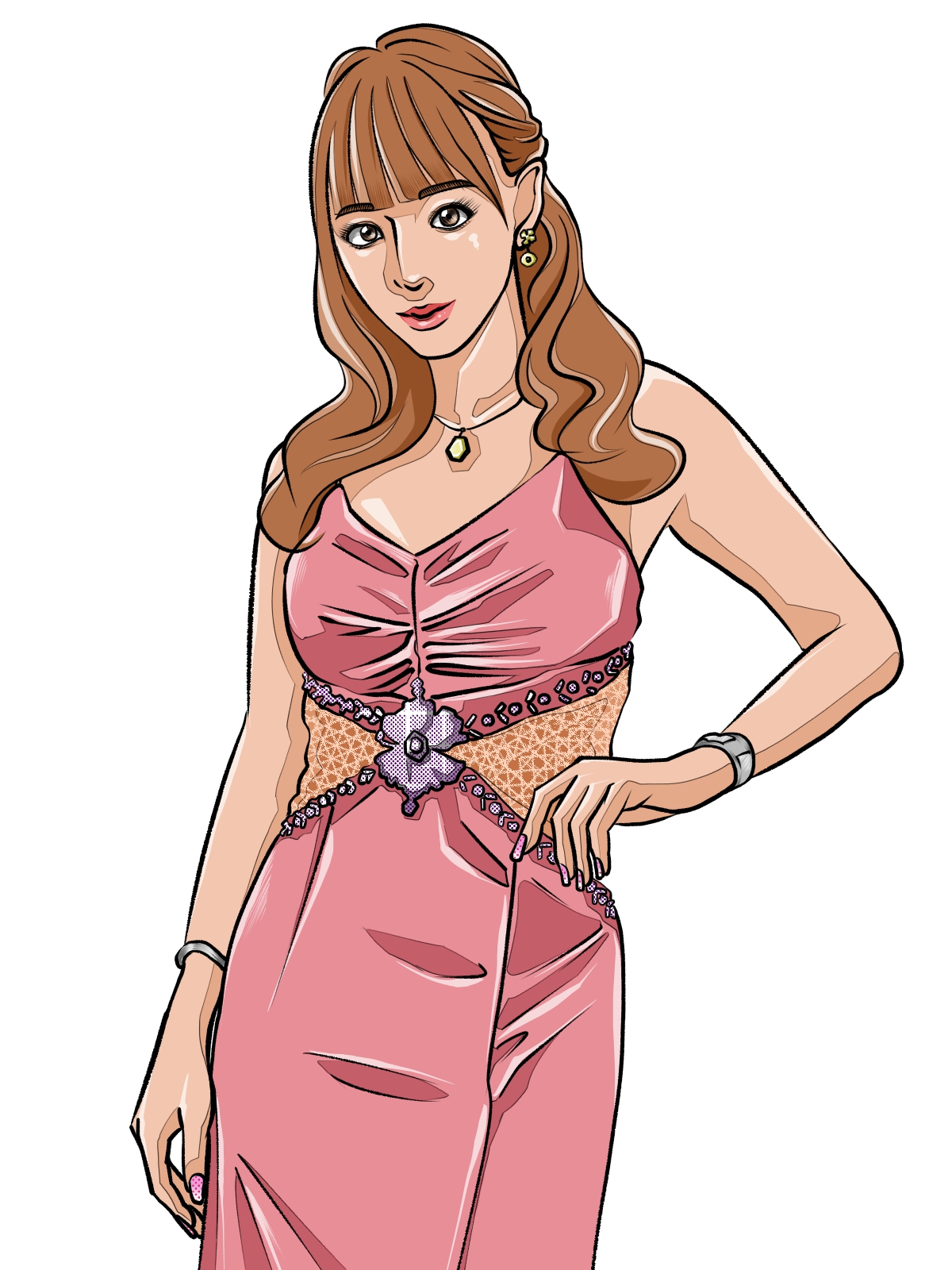
逆もまた然り
踊る大捜査線というドラマ。
あれは、あのドラマに出ている役者さんや、演出があってこその面白さな訳で、あのドラマを小説にしても、多分あのドラマの面白さは表現できないと思います。
織田裕二やいかりや長介が演じてこそのドラマであり、音楽や演出効果による臨場感なわけです。
原作のある作品を実写化する時に大切な事

- もっと映像の情報を信じた方がいい
- 役者さんを信じた方が良い
- 観客の想像力を、信じた方がいい
- 映像作品だから、台詞を減らす
- 映像であれば、説明台詞なんていらない
演劇や映像作品では、説明ゼリフが一番作品をつまらなくする要因の一つです。

小劇場での作品や、小さい映画祭で上映されている作品にも絶対面白いものがあります。
まぁつまらないのも多いですけどね!
お金を出すスポンサーの方々はもっと視野を広げるべきです。
周りに金の卵はたくさんあります。
結局スポンサーさんは、役者を初め監督さえも金儲けの道具としか見ていないんだと思うんですよね。
これからのスポンサーさんは、実力のある人を見つける能力と、育てる力が必要です。
そのための知識を学ぶ必要があるんです。
お金を使う方も勉強が必要なんです。
絶対に。
これからのエンタメの可能性

考えてみてください。
もしオリジナルの作品を作って、それが素晴らしい作品だったら、只の二番煎じで作った映画作品より、グッズやらなんやらで産み出せるお金は圧倒的に上のはず。
なのに近場の利益しか考えないから、駄作といわれるようなしょーもない作品を、無駄な時間とお金をかけて、世に吐き捨てることになるわけです。
もっと作りては苦労するべきなんです。
※お待たせしました。最後に紹介するおすすめの本はこちら⇩
『映画ライターズ・ロードマップ―“プロット構築”最前線の歩き方』です。
著者のウェンデル・ウェルマンは彼が書いた「ファイヤーフォックス」の映画化を機に、クリントイーストウッドと仕事をするようになった、ハリウッドの脚本を手掛けるプロ中のプロ。
そんな彼が書いたこの本は、脚本の書き方をプロットに焦点を当てて書いているテキスト本なのですが、驚くことに本の中でヒットする映画の法則が書かれています。
これがかなり具体的で、名作映画にもこの法則が見事に当てはまっている作品もあるくらいです。
映画好きの方、役者さん、脚本を書いている方、かなり役立つはずです。
映画のちがった新しい観方がみつかりますよ!
